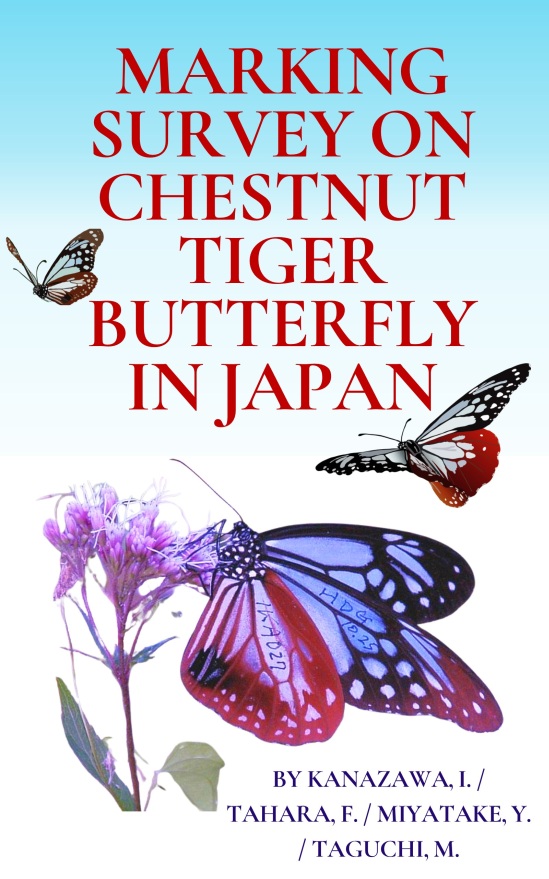アサギマダラの生態を観察する機会は春や秋の花畑や山でのマーキング以外にはそうそうあるものではありませんが、皆さんはどの程度アサギマダラの不思議に近づいてきたでしょうか?
春の海岸のスナビキソウで北上のアサギマダラを観察することができるようですが、秋にはアサギマダラの南下に伴ってフジバカマの花畑でアサギマダラをたくさん見る方も多いかも知れませんね。
メーリングリストやFacebookの書き込みで、アサギマダラの交尾を撮影したとか、オスのヘアペンシルを撮影したなどの情報が入ってくると、ちょっワクワクするものですね。滅多に見る機会がないからですよね。
長野県に住んでいても去年はなかなか山に行けなかった私ですが、今年になって7月31日にある方の別のチョウの調査に同伴して朝日村の林道鉢盛山線で、ゲートから鉢盛山登山口までの区間、車を走らせ、たまたま標高1465m付近で アサギマダラを観察する機会がありました。
イケマの周辺にいたアサギマダラを見つけ、思わずカメラを握り締めました。アサギマダラはイケマの葉裏に止まりましたので、葉の表から撮影。葉とアサギマダラが見えるように回り込みたかったのですが、動いてしまい、とりあえずピンボケでもいいからとシャッターを切りました。
2025.7.31-506 アサギマダラ イケマに産卵中11:15 これは直感ですが、イケマにアサギマダラがいたと言うことは、メスの産卵だと判断し、とっさにアサギマダラがいた葉に近づいて葉を裏返すと、やはり白い卵が。
2025.7.31-548アサギマダラの産みたての卵11:17 その同じ株の上の方の新芽には2つの卵も確認できました。同じ個体の卵なのでしょうね。3卵を確認できました。
2025.7.31-554小さなイケマの新芽にアサギマダラの卵を2卵確認11:17 アサギマダラはすぐ近くのクマザサの葉に止まり、さらに別の葉に移り、そこでじっとしています。産卵を終えて疲れ切ってしまったのでしょうか?
卵があったイケマの近くから動くこともなく、私が何度もカメラのシャッターを切ってもそのままです。うるさいシャッター音がするのに、逃げる様子もなく、疲れて眠りについたかのようです。
いつもでしたら捕まえてマーキングするのですが、そのアサギマダラを見た私はとてもマーキングする気になれず、そっと観察を続けました。
2025.7.31-612クマザサで休み続けるアサギマダラ11:15-11:24 メスのその個体の翅はボロボロで、浅葱色の部分にはシミも見えます。
翅の状態から考えれば、春に暖かいところで羽化したアサギマダラなんでしょうね。マークは確認できませんでしたが、どこから来たんでしょうね?メーリングリストで報告を出してくださる南の方の皆さんの顔が思い浮かびます。
産卵を終えたばかりのアサギマダラです。マークしようと思えば捕虫ネットもマーキング表もフェルトペンも持参していますし、素手で捕まえることも簡単にできました。でもアサギマダラの気持ちになれば、休ませてあげたいと思ったのは、女心からかも知れません。
でも、なぜアサギマダラは遠くに舞って行かなかったのでしょうか?人間が近くにいても平然と卵の近くに留まっているんです。これも女心なのでしょうか?いえ、親心があってのことだったりすれば、アサギマダラに感情があるってことですよね。そんなことってあるんでしょうか?
マーキングよりも観察を選び、10分弱その場所に私たちも留まりました。しかし目的があって林道に行っているので、いつまでもそのままでいられなく、私たちの方が先にその場所から移動することにしました。
葉っぱの表から撮影とはいえ、私がアサギマダラの産卵を確認したのは恐らく初めてのことです。
山のイケマの葉裏で卵は時々発見していましたが、産卵するアサギマダラは見たことがなかったように思います。
ヒメギフチョウやモンキチョウ、アゲハの産卵は何度も見ていますが、産卵は蝶の不思議な行動の一つですね。
どうやって幼虫の食草の葉を見分けるのでしょうか?株が小さくても見分けています。
産卵に葉の裏を選ぶのはなぜなのでしょうか?直射日光が当たらないからなのでしょうか?卵が雨に濡れないためでしょうか?
下を向いているに卵が葉っぱから落ちないのはなぜなのでしょうか?
小さな新芽に卵が二つもありましたが、食草が足りるのでしょうか?
人間でもお産には相当の体力を使いますが、チョウの場合はどうなんでしょうか?動かなくなるほどじってしていることを考えれば、やはり相当の体力を使っての産卵なのでしょうか?
7月末の産卵ですので、卵が成長して成虫になって、アルプスを越えて南に移動するのに、気温が下がりすぎる前の時期に成長が間に合うのでしょうか?
そんなメスのアサギマダラが2000km以上も移動した例もあることを考えると不思議がいっぱいでたまりません。
そんな素朴な疑問がいっぱいあるので調査をやめられないでいる私です。